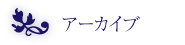カテゴリー
-
最近の投稿
アーカイブ
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月
- 2007年3月
- 2007年2月
- 2007年1月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年9月
- 2006年8月
- 2006年7月
- 2006年6月
- 2006年5月
- 2006年4月
- 2006年3月
- 2006年2月
- 2006年1月
- 2005年12月
- 2005年11月
- 2005年10月
- 2005年9月
- 2005年8月
- 2005年7月
- 2005年6月
- 2005年5月
- 2005年4月
- 2005年3月
- 2005年2月
- 2005年1月
- 2004年12月
『フランス人の夫のもとへ子供を返したくありません』
カテゴリー: 執筆
『フランス人の夫のもとへ子供を返したくありません』 はコメントを受け付けていません
コロナ禍で生活するということ
緊急事態宣言以降、数えてみたら、約半年が経つ。長かったような、あっという間だったような…。ただこの後も続くであろうことを思うと、どう考えても短いはずはないのである。
どの人の生活も大きく変わった。すでに書いたが、大学は結局オンライン授業(対話式と録画式があるが、当大学は後者。授業内容を予め吹き込む形式であり、ラジオ講座を頭に描くと分かりやすいと思う。)となり、皆それぞれに右往左往して(互いに情報交換をしている)、何とか前期を終えることができた。途中から一部、おおむね受講者50人以下の小規模授業やゼミ、実技講習を主として、対面授業になったが、同じ日に対面授業とオンライン授業があると、教える側も教えられる側も煩瑣である(もちろん、対面授業を行う場合には通勤通学に感染の危険がつきまとう)。周りの大学では前期いっぱい対面授業ゼロの所が多かったようだが、さすがに後期からは、一部の授業について対面式を並行して行う大学が8割になるという(残り2割は従来通り対面式のみで、これは地方の私立大学などに限られるであろう。)。対面式授業を少しでも持つようになると、1年生の場合、ようやくキャンパスに足を運びぶことになるわけだ。キャンパスライフを楽しむまではなかなかいかないにしろ、せっかく大学に入ったのだ、友達を作ってほしいなと思う。
前期試験の採点を済ませて1ヶ月余、少しばかり楽だったが(とはいえ、事務所には毎日出勤しているし、毎日やることがある)、今週、後期授業がスタートする(?来年1月)。第1回目の授業の録音はすでに済ませたが、久しぶりなので大変緊張した…。前期での貴重な経験を経て、要領も掴めたし、後期は以前より楽にやれるような気がするが、しかし後期もオンライン授業のみの私としては、このまま学生の顔を一度も見ないまま、一年が終わるのだなあと思うと、やはりなんとなく、寂しい。
オンライン授業の準備・実施は従来より遙かに大変だったりするのだが、ともあれ、物理的には通勤時間(片道1時間半以上)が不要となった。3月以降様々な行事・会合がおしなべて中止になったが、遅まきながら実施する場合には、ズームなど対話型オンラインに切り替わっている(裁判所もウェブ裁判である)。会場に行かないので、時間通りにパソコン前におればよく、移動時間も交通費も要らない。それでも仕事関係は、家だと気分が乗らないからと、夜はもちろん、週末でもあえて事務所には出ていたのだが、昨夜初めて、家でのズームにトライしてみたら、何のことはない、簡単である。こちら側も映らず、相手の映像も消して音声だけにできる(その分には大学の録画式授業と変わらない。ただ録画式の場合は何度でも聞くことができ、学生からはその点の評価が高いらしい)。
ズームの開始時間の少し前に帰宅し、さっさとご飯を作って食べ、講師の声を聞きながら洗濯も出来た(学生も他のことをしながら聞いているかもしれない…)。なんとまあ、有効に時間を使えることだろう。事務所ですべて聞いてから帰宅していたら、今から夕食・家事なのだから、昨夜は(テレワークをしている人などには当たり前のことなのに)大発見をした気分になった。今週はあと水曜と金曜の夜に入っているので、夕方帰宅し、自宅で聞くと決めた。いったん便利なのに慣れてしまうと、元に戻るのが難しくなるのは、考えたら、どんなことにも言えることである。
いろいろ来る案内も、今や当たり前のようにほぼウェブ参加である。出歩くなとのお達しあり、実際コロナ感染の危険あり、実施するとしたらそれが正解なのであろう。以前は、遠いし日程も合わないし(交通費も宿泊費も高いし…)行けなかったのが、移動することなく、その時間さえ空けておけばどこにいても参加できるのだ。時間と空間を超えて、ハードルがうんと低い世界が、コロナのお陰で一気に到来したわけである。ウェブ会議はもちろんのこと、ウェブ懇親会では参加者と話をすることも出来るのだが、人と直接に会う機会は格段に減った。会食など、個人的なものを除けば、ほぼ皆無である。あちこち不景気だらけだが、どうぞなんとか持ちこたえてほしいと願っている。
法律関係の雑誌は自分で購読しているものや、あちこちから送られてくるものなど、たくさんあって、放っておくとすぐに溜まってしまうのだが、今日読んだ「関弁連だより」に、向井千秋さんのインタビュー記事が載っていた。ご存じ、慶応病院のばりばり心臓外科医から日本初の女性飛行士に転身された女性だが、現在は東京理科大の特任副学長として教育に携わっておられるそうだ。「新型コロナウィルス感染拡大の現状に関して何かお考えはありますか」との弁護士の質問に対する以下の答えが、とても心に響いた。「宇宙から見ると地球って小さいんです。その小さい地球上で人間の活動範囲の幅は広がり、スピード感も増しているから、こういう感染症はあっという間に広まってしまう。私は、こういうパンデミックは、人類への警告であると思いますね。小さい地球上で人間同士が分断している場合ではなく、ダイバーシティ・インクルージョンを意識してみんなで力を合わせて協力しないと、人類は滅亡してしまうよ、という警告ではなかろうか」と。
カテゴリー: 最近思うこと
コロナ禍で生活するということ はコメントを受け付けていません
8月ももう終わり…証人買収罪初適用
5月の連休時帰省を諦めたが、お盆はちゃんと帰省した。お盆のど真ん中なのに、新幹線のすいていること!(奈良から東京に帰った知人いわく、深夜バスの客は自分一人だった!)交通機関はおしなべて大赤字であろう。観光施設その他も同じ。京都東山での結婚披露宴に参列してきたが、40度近い猛暑とはいえ、観光客らしい人はほぼ見かけなかった。
わずか4日の休みで9日間の夏期休暇だった。なにやかやとあったので休んだ感じはなかったが、17日から普通に働いている。通勤電車は相変わらず、すいている。猛暑も少し和らいで(とはいえクーラーはがんがんかけているので、クーラー病になりそうだ)、少なくとも夜は寝やすくなった。体調管理に気をつけながら、このあとの夏を乗り切りたい。
さて、本当に恥ずかしながら、証人買収罪なるものが3年前に新設されたことを、知らなかった。一体どこに? 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」7条の2である。この法律自体は、国会議員になった翌年(平成11年)8月、徹夜国会で通過させた思い入れのある法律なので基本は知っているつもりである。そのあと何度も改正され、しかしこの罪は、この法律に盛り込まれながらも、ひとり組織犯罪に適用されるわけではないのである! 同条1項は「次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること…の報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」とあり、これが組織犯罪に係る場合には2項で加重されて「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」になるという構成なのだ。そしてなんと、その初適用が、暴力団どころか、一般人どころか、国会議員の犯罪だったとは、ギャグみたいである。
IR(カジノを含む統合型リゾート)参入を巡って、中国関係企業から計1000万円弱の賄賂を受け取ったとして、逮捕起訴され、現在保釈中の秋元司衆院議員。せっかく保釈が取れたというのに、保釈条件もすっかり無視した挙げ句、人を介して贈賄者側に働きかけ、自分と会っていない(もちろんお金も渡していない)と嘘の証言をするよう頼んだというのである! その提供額はなんと2000万円!(本体額の倍以上あって、びっくり) 信じられない。そんなことをすれば、無罪を主張しているという本体の収賄罪を固めてしまうでしょ。贈賄者が黙ってその金額を受け取り、平気で偽証してくれると思っていたの?! まさか。そんな危ない橋、いくらお金を貰っても、こわくて誰も渡らないですよ。偽証は「3月以上10年以下の懲役」(刑法169条)、本体の贈賄(刑法198条。3年以下の懲役又は250万円以下の罰金)なんかよりもはるかに重い犯罪である。
案の定この人たちは、警察に相談をし、どうやらマスコミにも垂れ込まれて映像としても残っているらしいのである。買収を持ち掛けた秋元議員の知人3人が逮捕され(あと一人捜査中)、議員本人も逮捕されたが、またまた、自分は知らぬ存ぜぬと言い張っているらしい。そう言いさえすれば済むと、どうやら思っているらしいのだ。もしそうならば、仲に入った人たちがあなたに頼まれもしないのに、勝手に気を利かせて?よけいなことをやったわけですね?! 相手が議員に贈賄したとの供述がそもそもの嘘なのであれば、法廷でそれを丁寧に尋問して崩していけばいいのであって、別途お金を提供して嘘の証言を頼むのは筋違いにも程がある。2000万円は大金なので、その出所は明らかになるはずである。
今日は河井夫妻の初公判があり、やはり全面否認とのこと。金の授受自体は争えないので、もちろん趣旨否認である。買収目的ではなく、陣中見舞いその他の趣旨なのだと。前回の地方選挙の時は配っていないはずであり(自民党からそんな多額の資金も貰っていないし)状況からして買収目的だとしか考えられないが、だが被買収側は起訴されていないので(どころか立件もされていないという)、それが違法な司法取引であると弁護側は争い、なんと120人の証人がよばれるらしい。やはり100日裁判どころの話ではなかった。
ところで人間は、人の行動なり思考を推し量る際に、自分を基準にする傾向が大いにあると常々感じている。自分が腹が立つことならば、他の人も怒るだろうと思う。その推量が当たる時もあるが、外れる時も結構ある。あれ、腹立たないの? うん、こんなことで腹を立てていたら身がもたないよ…彼も悪気があったわけではないし…幸い大した被害もなくて軽く済んでよかったよ…フーン、寛容な人も世の中には多いのだと思ったりするのである(まあ確かに、私は短気だからね)。河井夫妻も秋元議員もきっと、自分と同じように他人を見ているのである。買収ではなく陣中見舞いで貰ったと、自分なら思う。そんな大金をくれるなら偽証くらい軽いものだと、自分なら思う。しかし残念ながら、それは世の中の常識に外れている。そんな人が国会議員になり、しかもまだ議席にあるのは、やはり大問題のように思われる。
カテゴリー: 最近思うこと
8月ももう終わり…証人買収罪初適用 はコメントを受け付けていません
「女帝エカチェリーナ」を読んで
コロナ自粛以降、夜も週末もたいてい空いているので、よく読書をしている。たまたま「イヴァン雷帝」(妻は次々と8人いたとか。拷問や残虐行為で悪名高い皇帝であり、最後は自分の息子まで殺してしまった)を読み、続いて同じ著者(アンリ・トロワイヤ)による「女帝エカチェリーナ」を読んだ。彼女には以前から大変関心がある。なぜ、ロシアの血が一滴も入っていない余所者(ドイツ人)がロマノフ王朝の皇帝になれたのか? あちこちで聞いても誰も答えてくれず、そのままになっていた…。
1729年生まれのゾフィはそれなりの公家の娘である。母親の亡兄がロシアのエリザヴェータ女帝(ピョートル大帝の次女)の婚約者であった縁で、独身で子供のいない女帝が、後継者として立てた甥(大帝の長女アンナの遺児。父親はドイツ人)ピョートルの嫁にと白羽の矢が立ったのだ。わずか14歳。ゾフィは、冴えない「はとこ」ピョートルを知っていたが、ロシアの皇妃になりたい一心で、自ら進んで赴き、ロシア式にエカチェリーナと改名、ロシア語を習い、父親の反対を押し切ってロシア正教に改宗する。翌年結婚。一つ上の夫は、兵隊ごっこが趣味で、プロシアのフリードリヒ大王に心酔しており、全くそりが合わないが、姑エリザヴェータ女帝の勧めもあって愛人を作り、結婚してようやく9年後に息子を産む(後のパーヴェル1世)。この子はすぐに姑に取り上げられ、終生母子は疎遠である。エリザヴェータが1762年、52歳で亡くなったときエカチェリーナは33歳。ピョートルが3世として即位する。根っからのドイツ人でロシアを侮蔑する夫は、軍隊を崇拝するプロシア式に変え、勝利を収めていた対プロシア戦を終結させてしまう。
軍や聖職者の多大の不満をバックに、彼女は、3人目の愛人(軍人)らを味方につけて軍によるクーデターを決行。哀れな夫は、愛人と共にドイツに隠棲することを熱望したが、彼女の愛人らによって殺害される(彼女自身が指示をしたわけではないだろうが、黙認し、かつ安堵したことは確かであろう。夫殺しの汚名はついて回る)。8歳の息子を帝位につけて自分は摂政…であれば順当だが、そんなつもりはまるでない。はなから自分が帝位につき、政治を執り行うつもりなのだ。息子を結婚させて嫡男アレクサンドルが誕生したときは、自分がされたのと同様、すぐに取り上げて自ら養育に当たる。長身で美男のアレクサンドル(1世)は彼女の大のお気に入り。将来ナポレオンをも翻弄することになるこの孫に直接帝位を継がせる意図だったが…実際は、彼女が1796年に67歳で亡くなったとき、跡を継いだのは最後まで仲が悪かった息子であった。息子は母親のやったことを全否定し、女性は帝位を継げないよう法律を作る。この息子は4年後、やはり軍のクーデターで殺害される。
話は変わるが、フランスには女王がいない。フランク人のサリカ法が女に不動産所有を認めない故である(周辺の〇〇公家では認めていたりするが)。スペインには偉大なイザベラ女王、オーストリアには偉大なマリア・テレジア女帝、またイギリスにもエリザベス1世やヴィクトリア女王がいるのだが(今もエリザベス2世である)。彼女たちは例外なく、王家の正統な跡取り娘である。マリア・テレジアはエカチェリーナと同時代人であり(テレジアが12歳上)、エカチェリーナのことは、王位簒奪者、夫殺し、淫乱女(生涯に知られているだけで12人の愛人がいた。中でポチョムキンとは秘密結婚をしていた言われる)…と大変嫌悪していたそうである。むべなるかな。であるのに、その長男ヨーゼフ2世はエカチェリーナと大変親しく、フリードリヒ大王と三者してポーランド分割に手を染め、マリア・テレジアを大いに悲しませている。
エカチェリーナは「回想録」を残している。啓蒙専制君主としての自分に大変誇りがあり(自分をヨーロッパ最高の知識人だと思っていたようだ)、ヴォルテール、グリム(グリム兄弟とは違う)、ディドロ(百科事典で有名)らヨーロッパ中で知られる知識人らと頻繁に文通を重ねていた。もちろん外交官らが詳しくその行状を書き留め本国に送ったりしているので、厖大なノンフィクションが作られるベースが存在するのである。これに限らず、歴史書を読むとき、外交官たちの記述はいつも大変参考になる。文通相手らは、エカチェリーナの歓心を買うためにか歯の浮くようなお世辞を並べ立てているが、実際のところはどうだったのだろうか。
外交官ハリスいわく、「彼女の宮廷は、次第に頽廃と背徳の舞台と化してしまった。…ポチョムキン公は彼女を完全に支配している。…」性格については「女帝は男のような精神、計画をあくまでも実行する力、とくに大胆に行動するという能力を持っておられるようだ。しかし深く物事を考えるとか、繁栄の中で節度を守るとか、的確に事態を判断するというようなもっと男性的な長所には欠けている。一方で、よく女性に見られる性格の弱さは、彼女にはきわめてはっきりと現れている。追従を好む人の常として自惚れ屋であり、聞くには不快だが為になる忠告には耳を貸さず、官能の喜びを求めてどんな身分の者でも恥じ入りそうな放蕩に身をもちくずす。」ヴェルサイユ政府に派遣されたコルブロンはもっと辛辣である。「この国はどのように治められているのか、どのように支えられているのか、とたずねる方もあろう。偶然により治められ、自然の平衡によって支えられていると、わたしはお答えしよう。それは巨大な塊がみずからの重みのために堅牢になって、あらゆる攻撃に耐え、腐敗と老化の絶えざる浸蝕だけにさらされているのにも似ている。」(「女帝エカテリーナ(下)」工藤庸子訳 中央文庫80?81頁)。
67歳で突然死ぬまで引きも切らず傍らに侍らせていた、美貌で若い愛人たち(あとの愛人たちはたいていポチョムキンが選んだ男である)に、肩書とお金を惜しみなく与える。宮殿や農奴数千人付きの土地も与える。啓蒙思想の一環として農奴解放を考えたこともあったようだが、貴族らの支持なくして帝位はなく、貴族らの大反対にあって、すぐに引っ込める。農奴は土地についているだけで、精神的には自由である??(なんとまあ、都合のよい為政者の論理であろう)。悲惨な状態にある農奴の解放は、結局彼女の曽孫アレクサンドル2世の時代にようやく手をつけられることになる。
実はロシアの女帝は、エカチェリーナが初めてではない。姑エリザヴェータはピョートル大帝の娘だから同列ではないにしても、エカチェリーナ1世とは、誰あろう、ピョートル大帝の未亡人である(エリザヴェータの母)。この人は、リヴォニアという所の農民の娘だったらしい(ピョートル大帝は最初の妻を修道院に押しやり、間に生まれた長男アレクセイを拷問死に追い込んだ)。もちろんロマノフ王朝の血など、ゼロであり,あえて言うならば貴族の支持、民衆の支持でしかないのだろう。たいていのロシア人があまり勉強せず、知性がどうやら欠けていたところにもって、フランス語やドイツ語が出来、古典も読んで当時最も進んでいる啓蒙思想にも染まり、個人的な交遊も深い女帝は、他の多くの欠点を補ってもなお、巨大な未開国であるロシアを、ヨーロッパ列強やトルコに対峙して統治するのに相応しいと思われていたのではないだろうか。彼女自身はロシアないしロマノフと無関係であったが、帝位はその子孫に引き継がれていく。
そもそもロマノフ王朝自体が以前より続いている王朝ではない。繋がりとしては、イヴァン雷帝の最初の妻が名門貴族ロマノフ家の出身だったということくらいである。イギリスやフランスその他の国では、後継者が途切れた場合、血筋を直近に遡り(イギリスのスチュアート朝がアン女王で途切れたときはもう少し遡り、ドイツから後継者を迎えてハノーバー朝としたが、それはカトリックを避けて新教徒に限った故である)、結局のところ、最初の祖先に戻るのだが、それとは違うのだ。もちろん中国のように、国をうまく治められない場合は天が覆して全く別の王朝にするという天治主義とも異なるが、今のロシアが人治主義と考えられているのに、あるいは類似するところがあるのかもしれない。日本の天皇制は連綿と続き、最も長い歴史を誇っているが故に尊敬もされているのだが、いつまで続くかとなると、かなり怪しいのは残念なことである。
カテゴリー: 最近思うこと
「女帝エカチェリーナ」を読んで はコメントを受け付けていません