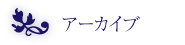ひとまず、当面の危機は回避できたようだ。ほっ。撤回や廃案とは言わず、秋の臨時国会で再度丁寧に(!)審議するとのことなので、油断も隙もあったものではないのだが。
民意の力の大きさを知らされたことは望外の喜びだった。検察官の定年とか検察庁法とかはどちらかというと世間的にはマイナーな話であり、さほど世論の関心をよぶとは思っていなかった。元検事総長や元特捜部長が集団で法務省に反対書を出したことが大きく取り上げられたが(それが「異例なことだ」というのは、それほど異例なことを内閣がやろうとしていた故である)、それも膨大な数の反対ツイッターの支えがあればこそである。デモまで出た。コロナ禍による自宅謹慎の故にニュースに敏感になったこともあるだろうし、この1月末から燻っている黒川問題で、かなりの人が懐疑心を抱いていることも影響しただろう。もちろんその背景として、モリカケ問題、桜問題、そしてコロナ対応の不味さ等々、政府に対する不信が募っていることが大いにあるはずだ。
国会は先週、今週中(5月15日)に衆院内閣委員会で強行採決するとの乗りで、野党が要望していた森法務大臣の出席要請にも応じていた。しかしそもそも、なぜ重大な懸念を孕むこの改正条項が、今になって大騒動になったのか? 法案を閣法として提出するためには、自民党の各部会でまず審議をする(その前に委員会に属する与党議員らの元に所管庁からレクがある)。そのうえで党の総務会を通したうえ、所管大臣が国会本会議で趣旨説明をし、各委員会での審議にかかるのだが、その前になぜ問題にならなかったのか? 確かに党と内閣の関係がずいぶんと様変わりをし、以前は部会での決議のハードルが高かったのだが、今は内閣から下ろしてくるのをただ追認するだけに成り下がっているとは聞いているのだが(内閣に属さない限り、議員でいるだけでは議決の数にしかならないわけだ)。
衆院ホームページを見て分かったことは、この改正案について、主を国家公務員の定年延長とし、検察庁法改正は刺身のつま程度の扱い、もちろんこの度の大問題になった幹部についての内閣の個別定年延長については何の記載もないのである! いわゆる束ね法案として国家公務員法との一括審理で自民党の内閣部会に上げたが、検察庁法についてはほとんど説明もなかっただろう。実際のところ法案をきっちり読みこむ議員も少ないし、たとえ分かったとしても、へえっで終わっていただろう。ようやく国会での内閣委員会審議で野党が異論を唱えたというわけだ。そういう、ある意味こすいことをやるのが役人の性でもあるのだが、肝心の法務省はいつこの法案を知ったのか。知らなかったとすれば暗愚だし、知っていながら何も言わなかったとすれば意気地なしである。黒川問題での対応に鑑みれば、内閣の一員である法務大臣の「鶴の一声?」で終わったのは想像に難くないが、他の公務員とは違い法曹資格があり、然るべき地位にいる者は職を賭してでも反対すべきだと思うのだが。そんな気骨ある者がいないとは、情けない限り…。
以前にも書いたが、2014年に安倍内閣の下、内閣人事局が発足し、審議官以上の高級官僚の人事が官邸主導で行われるようになった。そのことが、官僚が内閣に隷属し、内閣の意向を「忖度」するようになった根源である。その局長は元警察官僚であり、警察と経産省に引っ張られている内閣でもある。その目からすれば、しょせん検察も行政機関であり、他の国家公務員とことさら別異に扱う必要はないということかもしれない。従来内閣は、法務検察人事にはケチをつけなかったのだが、その一環としてか、ここ数年あからさまに異論を唱えるようになり、検察トップもだんだんと内閣に逆らわないようになってきたのかもしれない。結果、件の黒川氏は官房長が長く、事務次官も長く、東京高検検事長にも居座り、挙げ句は法に逆らって検事総長になろうとしているのである。
内閣による幹部検事の定年延長の基準が示されていない、今度は丁寧に示して、時間をかけて審議して、などと言っているが、事はそんなレベルの問題ではない。そもそも検察官の定年を65歳以上に延長しなければいけない理由(立法事実)などないのである。内閣へのへつらい(?)次第で総長の定年が3年も延びれば、総長になれない人が2人出る。そもそも検察が政権にへつらっていると思われること自体、世間の信頼を損なっているのである。となると、有為な人ほど検察官にはならない(ちなみに、裁判官は最高裁と簡裁判事が70歳、それ以外は65歳と決まっている)。法と正義に従って、国会議員や大臣の違法な行為を摘発できるというのが検察官任官の醍醐味であるし、それ故に国民も信頼できるのである。
次期国会に持ち越すというのは、もともとの発端になった黒川人事を諦めていないからではないか? 少なくとも、あの閣議決定を撤回すると言わないためには、その後付けとなったこの改正条項を意地でも維持するしかないのではないか。張本人の黒川さん、そろそろ表に出てきて、あなたの法的見解を明らかにして下さいとの書き込みに、大量の賛同者が出ていたが、私も本当にそう思う。いつまでも引っ込んでいないで、言うべきことがあればちゃんと言って下さい。ないのならば速やかに辞めて下さい。心からそう思っている。