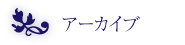毎月購読している雑誌は(法律関係を除いても)いくつかあるが、その中でも『月刊日本』は読むに足りる論考が結構網羅されていて、大変勉強になる。
6月号のタイトルは「政治劣化の根源は選挙制度にあり」。石破茂・武田良太(2人ともよく存じ上げている)・中島岳志(東京工業大学教授)の3人が取材に応じていた。政治資金問題はある意味些末なことであり、その根源には真っ当な政治家が選ばれていないという大きな問題が存在している。小選挙区制が失敗であり、中選挙区制に戻すべきだと私も確信しているが、石破氏の提言される「中選挙区連記制」は机上の空論のように思われる。選挙区を広げ、複数人を書いてもらう、連立政権誕生は織り込み済みなので、選挙民はどういう連立政権を組むかということも念頭に候補者を選ぶのだという。まさか。一般の市民がそこまで深く候補者を知ることが出来るはずもなく、そこまで要求するのであれば棄権が増えるだけである。あるいは適当に書かれてメチャクチャな政権が誕生するか…。
6月号の副題は「人口減少問題」であり、内田樹さんが取材に応じておられた。この方は70代前半、東京大学仏文学専攻の後、神戸女学院大学で教鞭を取っておられた。「思想家」として多数の著書がある。合気道や能など間口も広く、バランスの取れた視野から物事を論じておられ、いわゆる専門家の語り口とはまるで違う。『人口減少社会の未来学』(文藝春秋)は未読だが、内田氏は、人口減少は問題だと思っていないとのこと。従来人類の抱える問題は人口爆発であったのに、90年代を境に今度は人口減少が問題と言うようになった。先進国に限るとはいえ人口増が止まったのは「良かった」となるはずなのだが、誰もそう言わない。そもそも「適正人口」の提示もないのに、多い少ないというのは意味がない…。
氏いわく、問題になっているのは「人口」ではなく、「高齢層」と「若年層」の人口比率が非対称であること及び、都市に人口が一極集中して地方が過疎化している「人口分布の歪み」であると。前者については私も話をするときに取り上げているが、時間が経てば高齢者は死んでいくので当然に解消され、最終的に江戸時代の4000~5000万人位になればゆったりしてよいのじゃない? もちろんそれまでの間の労働人口減少が問題であるが、これは移民の受け容れではなく、高齢者と女性の活用で賄う以外にはない…というのが私の考えである(もちろんITやロボット活用も併行して)。移民を受け容れるのはそのときは良いが、移民も当然に年を取りいずれ保障が必要になるし、移民によってヨーロッパの各国が犯罪増加や社会対立の深刻な問題を引き起こしている先例に学ぶべきなのである。各国で(EU議会でも)右傾勢力が伸びているのは、移民問題が背景にある。
日本が例外というわけではなく、発展途上国でない国はすべて人口減少社会である。つまり少子化。氏いわく、先進国においては「親族を形成したい」という意欲が大きく減退したことが人口減少の大きな理由であると。すなわち、文明が進歩して、もう家族を作らなくても生きていけるようになったから…つまり「文明の進歩のコスト」であると。発展途上国に行くとよく分かるが、社会保障がないので、自らの老後のためには子供をたくさん作っておかないといけない、医療も生活環境も劣悪なので、それもたくさん作っておかないと間に合わない、年寄りはそう長くは生きられない…この社会では人口ビラミッドは正常形態であろうが、進歩した社会ではありえない。氏いわく、文明の進歩のおかげで、人類史上初めて我々は親族を形成しなくても、お金さえあれば、必要な生活資源はすべて市場で調達できるようになったのである。親族の解体は資本主義の要請でもあり、共同体が解体して個人がアトム化することで消費活動は異常に活性化したのだと。
振り返って検事時代の最初の頃は、男性検事は地方赴任の際、結婚していかないとご飯も食べられないとか言っていたけれど、そのうちにコンビニその他が続々と出来て、どこでもご飯を食べられるようになり、家事要員としての結婚は不要になったと記憶している。日本における男性の生涯未婚率は今や3人に1人(女性は5人に1人)という、信じられない数値を聞けば、少子化は当然の帰結であることが分かる。結婚して家族を持つという、かつては社会で一人前として認められるための必須の要請であったことが(ことに男性にはそれが強かったはずである)、独身男性が普通に周りにいるのであれば、もはや奇異な目で見られることも少ない。男性にとっての家事、女性にとっての経済力が、互いがくっつくモチベになっていたはずが、家事はお金で買えるようになり、女性も稼げるようになれば、手のかかる男性をあえて抱え込む必要もない。
子供がなかなか結婚しないのでどうしたものでしょう、とか聞いてくる人に私は答えるのだが(そもそも私に聞いてくることでもないと思うのだが(笑))、人間にはロールモデルが必要だ、自身の親が互いを敬い助け合って良い結婚生活を送っているのであれば、自分もああなりたいと願い、いい人を見つければ結婚をし、子供を作るでしょうと。残念ながら親が反面教師にしかならないのであれば、それは難しいはずですと。
この方の著作を読んでいて知ったのだが、文科省は漢文を削除する方向だとのこと(『一神教と帝国』集英社文庫)。もしかして既に削除されたのか? 恐ろしい…。小学校からの英語やら、投資やら裁判やらそんなことを教えて、大事な時間の配分はどうなるのか憂えていたのである! 20年以上前に歴史教科書問題をやっているとき、あまりに薄い選定教科書に唖然としたことがあるが、それでは基礎教養が全く身につかないはずである。国を挙げて薄っぺらな人間作りに精を出して、どうなるのだ。どこぞの大学では、実用英語は英語学校に丸投げする方向だとか(『街場の現代思想』文春文庫)。そのほうが確かに安くつくし先生も手慣れたものだろうが、これを突き詰めると、その学校で履修をしてもらった分を大学で単位認定すればよいのである。例えばラジオ講座を履修することで、あるいは本を読むことで単位認定してもよいくらいである。大学って、単位を取って、ただ卒業すればよい所なの!?
ネット検索は便利であるが、検索は自分の知った言葉を調べる手段である。英語の単語や国語にしても、検索すればその言葉の意味が分かるだけであり、反対に、従来の紙の辞書を引けばその周辺の言葉をも知ることが出来る。六法必携と言うと、ネットで条文検索が出来ると言うのが一定数いるが、それではその条文しか分からない(すでによく知った専門家であれば便宜的にそれでもよいのだが)。隣にどんな条文があり、どういう法律構造のどの位置にある条文なのかが分からなければ勉強にはならないし、さらに次を調べていくという学習も不可能である。氏いわく、大学でこれまでの紙のシラバスではなく電子シラバスにしたら、学生は自分の知りたい学科を見るだけになったと。紙でぱらぱら捲ったときに、あれえこんな学科があるんだ、こんな研究があるんだ、こんな有名人がいるんだという発見がないのだと。自分が知らないことを知る機会がなければ、知識教養は18歳までに知ったことに限定されてしまうと。しかも18歳までに大したものも会得していないわけだから、そのまま薄っぺらい大人になるだけである。なんともまあ、こわい。怖すぎる話である。